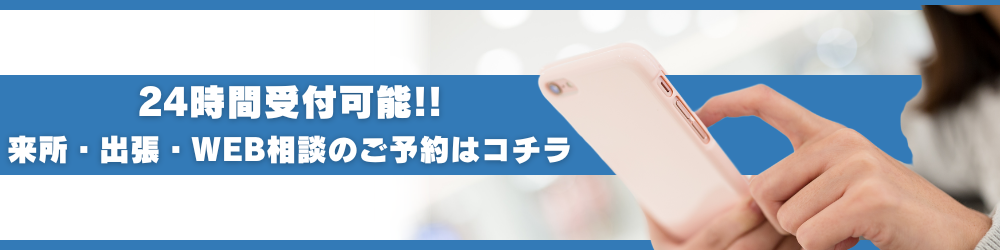非営利型一般社団法人の設立

一般社団法人は、一般社団法人の構成員である社員に剰余金を分配することはできず、非営利法人に分類されます。この一般社団法人の中でも非営利性を徹底した法人といわれるものがあり、税制上の優遇措置が受けられます。
すなわち、通常の一般社団法人であればすべての所得が課税対象となるところ、非営利型であれば、法人税法上の収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。例えば会費収入や寄付金は一般的に課税対象とならずメリットがあります。
非営利型の法人には、非営利性が徹底された法人(法人税法2条九の二イ、法人税法施行令3条1項)と共益的活動を目的とする法人(法人税法2条九の二ロ、法人税法施行令3条2項)の2種類があります。
目次
非営利型法人の要件
(1)非営利性が徹底された法人の要件
- 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
- 定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与する旨の定めがあること
①公益社団法人または公益財団法人
②公益認定法人5条17号イからトまでに掲げる法人 - 要件A及びBの定款の定めに反する行為(上記A、B及び下記Dの要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
- 各理事(清算人を含む。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
上記(1)要件の補足
A及びBについて
一般社団法人はもとから「社員に剰余金の分配又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない」(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)11条2項)とされ、さらに「社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない」(法人法35条3項)とされています。
ここでいう社員とは従業員のことではなく、株式会社でいうところの発起人や株主のような存在です。株式会社の株主は剰余金の配当を受ける権利を有しており、その意味で株式会社は営利法人とされ、剰余金の分配を社員に対して行うことができない一般社団法人は非営利法人とされています。
しかし、社員以外の者に剰余金や解散時の残余財産を分配したり、社員に対しても残余財産を分配することまでは禁じてられておらず、非営利性が徹底されているとはいえませんので、非営利性を徹底するためA及びBの定めを定款に置くことが求められています。
Aの定款の定めの具体例
「当法人は、社員その他の者に対し、剰余金を分配することができない。」
Bの定款の定めの具体例
「当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議も経て、公益社団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。」
Cについて
特別の利益を与えることとは、次に掲げるような経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付で、社会通念上不相当なものをいいます(法人税法基本通達1-1-8)。
- 法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する土地、建物その他の資産を無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付けていること。
- 法人が、特定の個人又は団体に対し、無利息又は通常よりも低い利率で金銭を貸し付けていること。
- 法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する資産を無償又は通常よりも低い対価で譲渡していること。
- 法人が、特定の個人又は団体から通常よりも高い賃借料により土地、建物その他の資産を賃借していること又は通常よりも高い利率により金銭を借り受けていること。
- 法人が、特定の個人又は団体の所有する資産を通常よりも高い対価で譲り受けていること又は法人の事業の用に供すると認められない資産を取得していること。
- 法人が、特定の個人に対し、過大な給与等を支給していること。
「なお、「特別の利益を与えること」には、収益事業に限らず、収益事業以外の事業において行われる経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付が含まれることに留意する。」とあります。
このCの要件を欠くことにより非営利性が徹底された法人ではない一般社団法人に該当することとなった場合には、「その該当することとなった日の属する事業年度以後の事業年度において同号の要件を満たすことはないことから、再び同項に規定する非営利型法人に該当することはない」(法人税法基本通達1-1-9)とされています。
Dについて
各理事について、当該理事と当該理事の親族等の合計人数が、理事総数に占める割合が三分の1とありますので、最低でも理事は3人必要となり理事2名以下では非営利性が徹底された法人となることができません。
つまり、例えば理事1名の一般社団法人であれば理事総数に占める当該理事の割合は1/1であり、1/3以下ではないのでDの要件を満たしません。
財務省令で定める理事と特殊な関係にある者とは次の者をいいます(法人税法施行規則2条の2第1項)。
- 当該理事(清算人を含む。以下同じ。)の配偶者
- 当該理事の三親等以内の親族
- 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該理事の使用人
- 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
- 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
一般社団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人の経営に従事している者は、当該一般社団法人の理事とみなしてDの要件を判定します(法人税法施行令3条3項)。
理事総数3人の非営利性が徹底された法人が理事が退任した場合、直ちにこの要件を満たさないものとして取り扱われるかですが、「非営利型法人が理事の退任に基因して当該要件に該当しなくなった場合において、当該該当しなくなった時から相当の期間内に理事の変更を行う等により、再度当該要件に該当していると認められるときには、継続して当該要件に該当しているものと取り扱って差し支えない。」(法人税法基本通達1-1-12)とされています。
(2)共益的活動を目的とする法人の要件
- 会員の相互の支援、交流、連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
- 定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること。
- その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
- 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
- 定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人及び公益財団法人若しくは公益認定法人5条17号イからトまでに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
- 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
- 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
上記(2)の補足
Aについて
同好会や同業者団体等を法人化するのに適した類型です。
Cについて
「主たる事業として収益事業を行っていないこと」の判定について、法人税法基本通達1-1-10は以下のとおり規定しています。
原則として、その法人が主たる事業として収益事業を行うことが常態となっていないかどうかにより判定する。この場合において、主たる事業であるかどうかは、法人の事業の態様に応じて、例えば収入金額や費用の金額等の合理的と認められる指標(以下1-1-10において「合理的指標」という。)を総合的に勘案し、当該合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるかどうかにより判定することとなる。
ただし、その法人の行う事業の内容に変更があるなど、収益事業の割合と収益事業以外の事業の割合の比に大きな変動を生ずる場合を除き、当該事業年度の前事業年度における合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるときには、その法人は、当該事業年度の開始の日において「主たる事業として収益事業を行つていない」場合に該当しているものと判定して差し支えない。(平20年課法2-5「二」により追加)
(注) 本文後段の判定を行った結果、収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えないとしても、そのことのみをもって「主たる事業として収益事業を行つていない」場合に該当しないことにはならないことに留意する。
Fについて
非営利性が徹底された法人の要件Cと異なり、社員総会の決議により残余財産を社員に分配することまでは禁止されていません。
特別の利益とは、非営利性が徹底された法人の要件Cと同様です(法人税法基本通達1-1-8)。
Dについて
非営利性が徹底された法人の要件と同様です。よって、理事は最低3人以上である必要があります。
一般社団法人の設立はお任せください
一般社団法人を設立手続きの流れ
| お客様に行っていただくこと | 当事務所が行うこと |
| 二人以上の社員(設立者)により法人の名称、事業目的等の定款の内容等を決め、法務局届出印を作成します。 理事1名以上の選任をします。 非営利型の場合は、3名以上である必要があります(上記非営利型法人の要件参照)。必要に応じ監事等も選任します。 下記必要書類等をご用意願います。 | 定款等の書類一式を作成し、お客様にご捺印をしていただきます。定款は電子定款としますので、収入印紙を貼付する必要がなく4万円の節約となります。 公証役場で定款認証の手続を行います。 |
| 登記完了後の書類を司法書士から受領 | 法務局へ登記申請し、完了後は登記事項証明書、印鑑証明書を取得します。 |
一般社団法人設立登記の必要書類等
お役様に用意いただきたい書類等
- 社員及び理事の印鑑証明書及び運転免許証等の本人確認書類の写し
- 監事の印鑑証明書又は住民票及び運転免許証等の本人確認書類の写し
- 法人の法務局届出印、社員及び理事の実印、監事の印鑑(認印可)
上記の書類及びお客様から定款の記載事項等をお聞きし、定款の作成・認証手続き並びに登記に必要な一切の書類を当事務所で作成します。
一般社団法人の設立登記等の費用
| 内容 | 報酬(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 一般社団法人の設立登記一式 (定款作成認証手続・議事録等登記に必要な一切の書類作成を含む。) | 110,000円 基本的なものは上記、複雑なものは都度見積もり | 登録免許税:60,000円 定款認証手数料:約52,000円 登記簿謄本代、送料等その他実費 |
一般社団法人の設立は、経験豊富は当事務所にお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
投稿者プロフィール

- 司法書士・行政書士
- 開業22年目となる名古屋市の司法書士・行政書士です。元設備保全マン、趣味は音楽、ギター、テニス、語らうことです。人には親切にをモットーとしており司法書士を天職だと思っています。自分の勉強を兼ねた業務上の情報を中心に執筆しています。
最新の投稿
 一般社団法人設立登記2025年11月25日非営利型一般社団法人の設立
一般社団法人設立登記2025年11月25日非営利型一般社団法人の設立 商業・法人登記2025年10月1日みなし解散通知書が届いた場合の対処法
商業・法人登記2025年10月1日みなし解散通知書が届いた場合の対処法 不動産登記2025年9月20日みなし解散法人と抵当権抹消登記
不動産登記2025年9月20日みなし解散法人と抵当権抹消登記 司法書士ライフ2025年9月13日富士山に登ってきました
司法書士ライフ2025年9月13日富士山に登ってきました